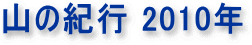休暇を利用して、南会津から越後にかけての個性的な山を三座巡ってみた。
天気はずっとすっきりしない状態だったが、紅葉はそれなりに楽しめた。 今年は残暑が長く続いたので、紅葉の色付きはどうかなと思っていたが、山の上のほうはまずまずの綺麗さだった。
|
10月11日 会津朝日岳 天候: 雨のち曇時々晴
前夜のうちにいわなの里の先の駐車場に入り、車中泊。 夜中はかなり強い雨が降り続きどうも気分が良くない。朝起きるとすでに6台くらい車が来ており、意外と登山者が多い山だなという印象。出発5:50。
しばらくは赤倉沢に沿って登って行く。 一旦は止んでいた雨がまた降り出すが、道は整備された良い道で歩きやすい
。
叶ノ高手の手前の尾根に出る頃になると雨も止んで、上空は青空も広がって来る。しかし山の上の方は雲に覆われたまま。叶ノ高手着8:40。この辺りは紅葉も綺麗に色付いている。
叶ノ高手の先で会津朝日岳の見られる場所がある。頂上付近は雲で霞んでいるが、荒々しい岩場を巡らせなかなか立派な山容。
会津朝日岳の本格的な登りは避難小屋から始まるが、待っていれば山頂の雲も晴れるかと、避難小屋で30分くらい待機したが、結局あきらめて頂上に向かう。
頂上直下は岩場交じりの急斜面で最後にどっと疲れる。 会津朝日岳頂上着10:40。やはり雲の中で何も見えない。
下って来るとまた日の射す良い天気となるが、振り返って見る頂上部だけはやはり雲の中。結局最後まで頂上部は晴れなかった。
駐車場に戻ったのが14:15。
|
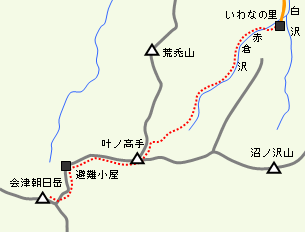
 |
 |
尾根に出た辺り
青空が見え出す
|
叶ノ高手付近の紅葉
|
|
|
 |
 |
 |
 |
叶ノ高手からの会津朝日岳
|
会津朝日岳近付く
奥に見える岩場は
北壁と呼ばれるらしい |
北方の展望
|
南会津の山々
どれが何山かよく分からない
|
|
|
|
 |
10月12日 御神楽岳(途中まで) 天候: 曇
御神楽岳への登山コースは3本あるが、その中で難路と言われているが、一番豪快な眺めが楽しめそうな広谷からのコースを選んでみた。
広谷から蝉ヶ平の集落を抜けて、広谷川沿いの林道を3kmくらい入った所が林道の終点。
車が4〜5台泊まれるスペースがある。 前夜のうちにここ着いて車中泊。
朝起きるといつの間にかもう1台車が停まっていた。 5:40出発。 山道は広谷川左岸のかなり高い所を巻くように細々と付けられている。
足場も悪くて踏み外すと只では済まないような場所も多い、気の抜けない道。
1時間余りで湯沢出合に着く。 6:50。 ここからいよいよ尾根に取り付く。
尾根を登るにつれ、湯沢奥壁の凄まじいばかりの光景が広がり、目を奪われる。
|
|
 |
 |
 |
 |
広谷川沿いの道
(土の露出している所が道)
|
湯沢出合の渓流
この辺りの岩は鮮や
かなシアン色で美しい |
覆いかぶさるように
広がる湯沢奥壁
|
高頭に登る嶮しい尾根
|
|
高頭(たかつむり)へ登るこの尾根はなかなかにハードである。 終始岩場に次ぐ岩場の連続。先を眺めても「ほんとうにこんな所を登るの」と思ってしまう。鎖やロープも張られているが、立木や木の根のような固定するものがある所だけ張ってあるという感じで、無い場所でもけっこう難しい。
最後まで急登が続き、しかも蒸し暑い。汗だく状態で高頭に着いたのが9:40。ここで大休止。
高頭から先は岩場こそ無いが、余り刈払いのされていない半分ヤブ漕ぎのような道で、時間ばかりかかる。 湯沢ノ頭着11:10。 ここでようやく御神楽岳の本峰を目にする。 全身岩の鎧をまとったような、1400m足らずの標高とは見えない豪快な姿。 この後すぐに雲に隠れて見えなくなり、ぎりぎりのタイミングだったみたい。
湯沢ノ頭で時間切れということで(息切れというのもある)引き返す。
高頭12:20。ここから尾根を慎重に下り、湯沢出合に降りたのが14;15。さらに山道を辿って林道終点に戻ったのが15:50。
けっこう良い時間になってしまった。
登山届を見ると、もう一台の車の人は高頭で引き返したようだ。 別にもう1人来ていたが、この人もすでに下山したもよう。
やはりこのコースから御神楽岳に日帰りで往復というのはかなり厳しそうである。
このコースからの主な眺めはいちおう味わえたので、次は只見側からのコースでもう一度登ってみたい気がする。
|
 |
 |
 |
 |
霧湧く山腹
|
ミヤマママコナ
|
奥壁上部の眺め
|
湯沢ノ頭を仰ぐ
|
 |
 |
 |
 |
高頭からの湯沢ノ頭
|
湯沢ノ頭からの御神楽岳
これも岩の鎧で覆われている
|
マツムシソウ |
雲に覆われ始めた岩場
帰りの尾根から
|
|
|
10月13日 八海山 天候: 晴のち曇
今日は東京に帰る日だが、朝から久しぶりに天気も良いし、ロープウエーを利用できて比較的短時間で登って来られる八海山に登ってから帰ることにした。
寄り道と言うほどには軽くない山ではあるが。
ロープウエーの始発に乗り込んだ登山者は20人くらい。 山上駅を降りて、前後して登り始める。
8:40。 この辺りの地面は砂利のようなものは無くて、すべて赤土の粘土。それが雨でぬるぬるになった状態の泥道が続く。
女人堂辺りからは登りの傾斜も急になり、道も岩の道になる。薬師岳の登りは女人堂から標高差300m。今日もまた蒸し暑い中、急坂が続く辛い登りだが、登るにつれ紅葉も鮮やかになってくる。
薬師岳に登り付くと目の前に八ツ峰が望まれる。10:35。紅葉もこの辺りが盛り。 |
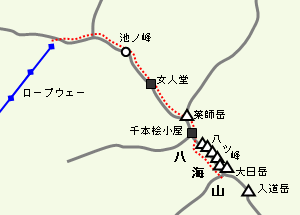
 |
 |
山麓からの八海山
|
薬師岳からの千本桧
小屋と八ツ峰・地蔵岳
|
|
|
八ツ峰は地蔵岳、不動岳、七曜岳、白河岳、釈迦岳、摩利支岳、剣ヶ峰、大日岳の8峰から成り、その間19ヶ所の鎖場がある(ロープウエーの切符にある説明)。
8つのピークの垂直に近いアップダウンの繰り返しは、けっこうスタミナと神経を使わされるが、変化に富んだスリリングな登高はなかなか楽しい。
最後のピークが大日岳で、ここが八海山山頂ということ。 11:45着。
大日岳から入道岳の間は、登山道が崩れて通行不可となっていて、残念ながら入道岳までは行けない。
ここから引き返す。 摩利支岳と釈迦岳の間から八ツ峰迂回路に下れるので、迂回路を取って千本桧小屋に戻る。
この頃になると山はすっかり雲に覆われて何も見えなくなる。 今日もまたタイミングが良かった。
千本桧小屋12:35。薬師岳まで来ると人が多い。 ここまでならロープウエーを利用して気軽に来られるということで、
急に辺りの雰囲気が俗っぽくなった感じ。薬師岳から下ってロープウエー乗り場に戻ったのが14:10。
|
 |
 |
 |
 |
| 雲をまとった越後駒ヶ岳 |
地蔵岳からの不動岳 |
不動岳を行く登山者
|
釈迦岳からの白河岳
|
 |
 |
 |
 |
釈迦岳からの大日岳
|
霧に浮かび上る摩利支岳 |
摩利支岳からの釈迦岳 |
大日岳から見下ろす
|
|